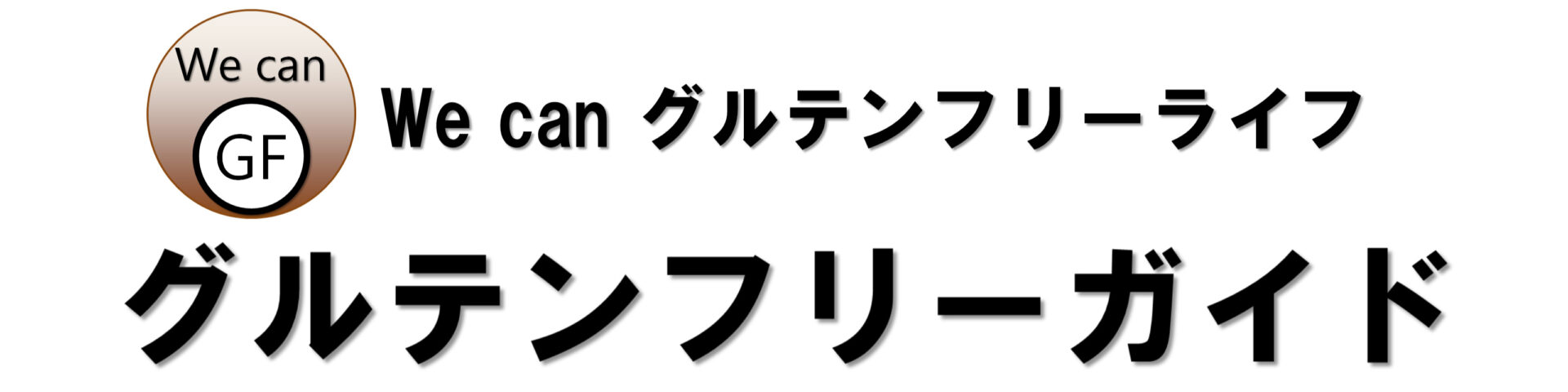ポストハーベスト農薬は農産物の収穫後に使うもので、輸入フルーツに使われる防カビ剤と、輸入穀物に使われる防虫剤があります。輸入農産物は収穫してから店頭に並ぶまで時間がかかるため、品質の低下やカビの発生を防ぐために使われます。農薬という名前ですが、食品添加物の扱いで、残留基準値が決められており、上回ったものは流通しません。
- 1 ポストハーベスト農薬とは
- 2 ポストハーベスト農薬の発がん性
- 3 ポストハーベスト農薬に関する情報のウソ・ホント
- 4 ポストハーベスト農薬一覧:使用される農産物と発がん性
- 4.1 オルトフェニルフェノール(OPP):防カビ剤/発がん性不明
- 4.2 チアベンダゾール(TBZ):防カビ剤/発がん性あり
- 4.3 イマザリル(エニルコナゾール):防カビ剤/発がん性あり
- 4.4 フルジオキソニル:防カビ剤/発がん性なし
- 4.5 ピリメタニル:防カビ剤/発がん性あり
- 4.6 マラチオン(マラソン):殺虫剤/発がん性あり
- 4.7 ピペロニルブトキシド:殺虫剤/発がん性不明
- 4.8 ピレトリン:殺虫剤/発がん性なし
- 4.9 リン化アルミニウム、リン化マグネシウム:殺虫剤
- 4.10 クロルピリホスメチル:殺虫剤/発がん性なし
- 4.11 フェニトロチオン(スミチオン):殺虫剤/発がん性なし
- 4.12 ピリミホスメチル:殺虫剤/発がん性なし
- 4.13 ジクロルボス(DDVP):殺虫剤/発がん性なし
- 5 まとめ
ポストハーベスト農薬とは
ポストハーベスト農薬とは、ポスト(後に)+ハーベスト(収穫)+農薬、つまり農産物の収穫後に使用する農薬のことです。
農薬は、農産物を植える前に土壌や種子を消毒したり、農産物が生育中に虫に食べられたり病気になるのを防ぐために用いられるもので、通常は収穫後には使いません。ところが海外で生産される農作物は、輸送・保管の間に品質が低下するのを防ぐため、収穫後に農薬が使われることがあります。これがポストハーベスト農薬です。
ポストハーベスト農薬は、農薬ではなく「食品添加物」の扱いになっていることをご存じでしょうか。農産物の生産のために使用されているのではなく、「食品の保存」のために使用されているからてす。
そのため食品衛生法で、
- 使用してはいけないもの(食品添加物として指定されたもの以外は使用禁止)
- 一定量以上、残留してはいけないもの
に分けられています。
ポストハーベスト農薬を使う目的は次の 3 つです。
- 農産物の品質の低下を防ぐ。
- 農産物の腐敗等による廃棄を減らし、農産物を安価に供給する。
- 輸送・保管中に発生したカビなどによる食中毒を防止する。
収穫した農産物を新鮮なうちに食べるのであれば、ポストハーベスト農薬は使用する必要がありません。海外で生産された農産物は、消費者に届くまでに時間がかかるので、ポストハーベスト農薬を使わざるを得ないのです。

ポストハーベスト農薬の発がん性
ポストハーベスト農薬には発がん性や催奇形性があるから、危険!という情報をよく目にします。一部のポストハーベスト農薬に発がん性や催奇形性が報告されているのは事実です。
ただ、ポストハーベスト農薬として使用されているものには、一日摂取許容量(ADI)と残留基準値が定められています。一日摂取許容量(ADI)は人が一生の間、毎日摂り続けても安全な量で、残留基準値は多くの場合、その 1/100 に設定されています。
言い換えると、残留基準値の最大量の 100 倍の量を、一生の間、毎日摂り続けたとしても、健康上の問題は生じないということです。
発がん性や催奇形性の有無を調べる実験は、通常では考えられない高濃度で行われるのが普通です。ですから、ポストハーベスト農薬という化学物質に発がん性や催奇形性があったとしても、農作物に付着している残留物で、がんになることはありません。
だからといって、ポストハーベスト農薬が 100 % 安全かというと、そうとも言えません。ポストハーベスト農薬は、もともと自然界に存在していたものではなく、人間が人工的に作り出したものです。人体や環境にどのような影響があるのか、完全に調べることなど、不可能です。ポストハーベスト農薬もそれ以外の農薬や食品添加物も、摂らずに済むなら、その方がよいでしょう。
個別のポストハーベスト農薬の発がん性については、下の、ポストハーベスト農薬一覧をご覧ください。
ポストハーベスト農薬に関する情報のウソ・ホント
ポストハーベスト農薬の有害性、危険性についてさまざまな情報がありますが、科学的に正しいものと間違っているものがありますので、整理しましょう。
さきに断っておきますが、筆者はポストハーベスト農薬の使用に賛成ではありません。残留しているしていないにかかわらず、農薬の使用はしないほうがよいに決まっています。ただ現在の日本の食料自給率を考えたとき、海外からの農産物の輸入は避けられず、それに伴うポストハーベスト農薬の使用はある程度やむを得ないと考えています。この点については最後に触れたいと思います。

収穫後に使用されるため農産物への残留量が多い
ポストハーベスト農薬は、収穫した農産物の保管中の倉庫の中や、輸送中の貨物船の中で使用されます。そのため検査を行う時点での残留量が多いというのは事実です。
例えば小麦に使用される殺虫剤クロルピリホスメチルの基準値は、
- 国際基準と日本の国内基準は、ポストハーベスト農薬として使用することを前提としているため、10 ppm
- アメリカの基準は、ポストハーベスト農薬として使用しないことを前提としているため、6 ppm
と、同じ農薬を同じ農産物に使用するにも関わらず、異なる値になっています 9)。
収穫前に使われる農薬よりポストハーベスト農薬の方が危険
どちらも有害危険性(安全性)は同じです。農薬がいつ使われたかではなく、農産物にどれだけ残っているかで、有害危険性は判断すべきです。
国が決めた検出基準値は正しくない
食品衛生法で、農薬とポストハーベスト農薬(食品添加物)の検出基準値が決まっており、これを上回った農産物は流通させることができません。
この検出基準値か本来ゼロであるべきで、検出基準値そののものが信用できないという意見もあります。
この検出基準値(残留基準値)というのは、化学物質の一日摂取許容量に基づいて決められています。化学物質を摂取しても人体に何ら作用がない量を無有害作用利用といいますが、残留基準値はこれの 1/100 に設定されていることが多いです。すなわち仮に残留基準値の 100 倍 摂取しても、人体に影響がない、ということです。このように残留基準値は科学的根拠に基づいて決められているので、信用できると考えます。
ポストハーベスト農薬は日本では使用が禁止されている
禁止されていません。
例えば果物などの保存性を向上させるために、農薬と同じ成分の薬剤で処理されることがあります。温室効果ガス削減のために使用されなくなりましたが、2013 年まではクリシギゾウムシを防除するため、収穫した栗の実を臭化メチルで燻蒸していました。
海外で使用されるポストハーベスト農薬には実質制限がない
日本で使用が禁止されている農薬が使われている場合には、輸入ができません。これはポストハーベストに限らず、すべての農薬についていえることです。
海外で使用するのだから、日本の規制とは関係なく何を使用してもよい、というわけではありません。ただ国によって基準が異なる場合があります。その場合、誤って輸入されてしまう場合があります。輸入農産物の残留農薬は、全数検査しているわけではないので、検査をすり抜けて、店頭に並ぶ可能性はゼロではありませんし、実際に起きています。
じゃがいもにはポストハーベスト農薬が使用されている
これは全くのウソです。
じゃがいもは病害虫の蔓延のため、主要国からの輸入が禁止されており、それ以外の国からの輸入でも、輸入時の検査に加えて、隔離栽培(国の施設で、輸入したじゃがいもを植えてウイルス病等の検査を行う。)が必要になります 10)。
そのため、生のじゃがいもの輸入は行われていませんので、ポストハーベスト農薬も使用されていません。冷凍ポテトフライや馬鈴薯でんぷん、加工でんぷんは輸入されていますが、これらの製品は海外で加工されるため、ポストハーベスト農薬を使う必要がありません。
ポストハーベスト農薬一覧:使用される農産物と発がん性
ポストハーベスト農薬として使われているのは、防カビ剤と殺虫剤です。防カビ剤が使われているのはかんきつ類を中心とした果物、防虫剤が使われているのは小麦、米などの穀物です。なおこの記事で示している残留基準値は、残留農薬基準値検索システム1) によるものです。

オルトフェニルフェノール(OPP):防カビ剤/発がん性不明
輸送中や保管中にカビが生えるのを防ぐため、かんきつ類の表皮に散布します。オルトフェニルフェノールナトリウムも同じように使用されます。さまざま細菌に殺菌効果を示すチアベンタゾール(TPZ)と併用すると効果が高まります。
ポストハーベストで使用が認められている農産物はかんきつ類のみです。使用されている可能性がある農産物と残留基準値は下記の通りです。
果物を袋に入れて売る場合は、原材料表示欄に「オルトフェニルフェノール」を使用している旨、表示しなければなりません。
一方、ばら売りの場合は原材料表示は免除されるのですが、防カビ剤として使用されるオルトフェニルフェノール(OPP)、チアベンダゾール(TBZ)、イマザリル、ジフェニル、フルジオキソニルについては、ばら売りであっても、使用していることを表示をしなければならないきまりになっています。1 日許容摂取量(ADI) は、1 mg / kg-体重です。
使用される農産物と残留基準値
- みかん:10 ppm
- なつみかん:10 ppm
- レモン:10 ppm
- オレンジ(ネーブルオレンジを含む):10 ppm
- グレープフルーツ:10 ppm
- ライム:10 ppm
発がん性
世界保健機関(WHO)の国際がん研究機関(IARC)では、化学物質などについて発がん性リスクを評価し、5 段階に分類して公表しています。ここでオルトフェニルフェノールはグループ 3 の「ヒトに対する発がん性について分類できない」に、オルトフェニルフェノールナトリウムは グループ 2B の「ヒトに対して発がん性があるかも知れない」にそれぞれ分類されています 2)。
チアベンダゾール(TBZ):防カビ剤/発がん性あり
いろいろな細菌に対し抗菌効果を示す薬剤で、殺菌剤としても使われます。ポストハーベストで使用が認められている農産物はかんきつ類とバナナです。かんきつ類は表面に光沢を与えるワックスに TBZ を混ぜて、収穫した果物を漬けることで使用されます。バナナは TBZ の溶液に漬ける場合とスプレーする場合があります。1 日許容摂取量(ADI) は、0.1 mg / kg-体重です 2)。
使用される農産物と残留基準値
- みかん:10 ppm
- なつみかん:10 ppm
- レモン:10 ppm
- オレンジ(ネーブルオレンジを含む):10 ppm
- グレープフルーツ:10 ppm
- ライム:10 ppm
- バナナ:3 ppm
発がん性
繁殖能に対する影響はありませが、遺伝毒性にあります。発がん性試験において、ラットで甲状腺ろ胞細胞腺腫及び包皮腺腺腫の発生頻度増加が認められました。発生毒性試験において、ウサギでは母体毒性の認められる用量で胎児に奇形の発生頻度増加が認められていますが、ラットでは催奇形性は認められていません 11)。
イマザリル(エニルコナゾール):防カビ剤/発がん性あり
強い防カビ効果があります。ポストハーベストで使用が認められているのはオレンジを除くかんきつ類とバナナです。かんきつ類は表面に光沢を与えるワックスにイマザリルを混ぜて、収穫した果物を漬けることで使用されます。バナナはイマザリルの溶液に漬ける場合とスプレーする場合があります。
使用される農産物と残留基準値
- なつみかん:5 ppm
- レモン:5 ppm
- グレープフルーツ:5 ppm
- ライム:5 ppm
- バナナ:2 ppm
発がん性
EU(欧州連合)による発がん性評価では、ヒトに対する発がん性が疑われる物質に分類されています 12)。
フルジオキソニル:防カビ剤/発がん性なし
さまざまな種類のカビに効果があります。ポストハーベストで使用が認められているものは、以下の農産物です。また 1 日許容摂取量(ADI) は、0.33 mg / kg-体重です 3)。
使用される農産物と残留基準値
- なつみかん:10 ppm
- レモン:10 ppm
- オレンジ(ネーブルオレンジを含む):10 ppm
- グレープフルーツ:10 ppm
- ライム:10 ppm
- りんご:5 ppm
- 西洋なし:5 ppm
- マルメロ(西洋カリン):5 ppm
- びわ:5 ppm
- もも:5 ppm
- ネクタリン:5 ppm
- あんず(アプリコットを含む):5 ppm
- すもも(プルーンを含む):5 ppm
- キウイ:20 ppm
発がん性
発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性および生体において問題となる遺伝毒性は認められていません 3)。
ピリメタニル:防カビ剤/発がん性あり
カビの増殖を抑えます。ポストハーベストで使用が認められているものは、以下の農産物です。また 1 日許容摂取量(ADI) は、0.17 mg / kg-体重です 4)。
使用される農産物と残留基準値
- なつみかん:10 ppm
- レモン:10 ppm
- オレンジ(ネーブルオレンジを含む):10 ppm
- グレープフルーツ:10 ppm
- ライム:10 ppm
- りんご:14 ppm
- 西洋なし:14 ppm
- マルメロ(西洋カリン):14 ppm
- もも:10 ppm
- あんず(アプリコットを含む):10 ppm
- すもも(プルーンを含む):10 ppm
発がん性
繁殖能に対する影響、遺伝毒性、催奇形性は認められていませんが、発がん性はあります 4)。

マラチオン(マラソン):殺虫剤/発がん性あり
有機リン・有機硫黄系殺虫剤として使われる農薬で、穀物を食べる虫を殺すために使用されます。日本では家庭園芸用にホームセンターで売られており、アブラムシ、ハダニ、アオムシ、ウリハムシなど、さまざまな害虫の駆除に使われます。また 1 日許容摂取量(ADI) は、0.29 mg / kg-体重です 5)。
これは体重 50 kg の人の場合は 15 mg となり、例えばマラチオンが 8 ppm 含まれる小麦を食べるた場合、小麦を 1 日 1.9 kg 食べないと、この値にはなりません。
使用される農産物と残留基準値
- 小麦:8 ppm
- 大麦:2 ppm
- 米:0.1 ppm
日本が小麦を輸入しているアメリカ、カナダ、オーストラリアにおけるマラチオンの小麦への残留基準値は、日本と同じ 8 ppm です。
発がん性
繁殖能に対する影響、催奇形性、発達神経毒性および生体において問題となる遺伝毒性は認められていません。またマウスでは発がん性が認められましたが、ラットでは認められていません 5)。
ピペロニルブトキシド:殺虫剤/発がん性不明
ポストハーベストの殺虫剤として以下の穀物への使用が認められています。
使用される農産物と残留基準値
- 小麦:24 ppm
- 大麦:24 ppm
- 米:24 ppm
日本が小麦を輸入しているアメリカ、カナダ、オーストラリアにおけるピペロニルブトキシドの小麦への残留基準値は日本より厳しい 20 ppm となっていますが、国際基準では 30 ppm です。
発がん性
世界保健機関(WHO)の国際がん研究機関(IARC)の発がん性リスク評価では、グループ 3 の「ヒトに対する発がん性について分類できない」に分類されています 2)。
ピレトリン:殺虫剤/発がん性なし
蚊取り線香の殺虫成分と同じ化学物質で、ポストハーベストの殺虫剤として以下の穀物への使用が認められています。
使用される農産物と残留基準値
- 小麦:3 ppm
- 大麦:3 ppm
- 米:3 ppm
日本が小麦を輸入しているアメリカ、カナダ、オーストラリアにおけるピレトリンの小麦への残留基準値は日本と同じ 3 ppm です。
発がん性
蚊取り線香にも用いられている成分であり、調べた範囲では発がん性があるとの情報はありませんでした。
リン化アルミニウム、リン化マグネシウム:殺虫剤
いずれも粉末ですが、大気中の水分と反応して毒性の強い気体のホスフィン(PH3)を生じるため、殺虫剤(燻蒸剤)として使われます。ポストハーベストで以下の穀物への使用が認められています。となりの数値はホスフィンとしての残留基準値です。
使用される農産物と残留基準値
- 小麦:0.1 ppm
- 米:0.1 ppm
日本が小麦を輸入しているアメリカ、カナダ、オーストラリアにおけるホスフィンの小麦への残留基準値は日本と同じ 0.1 ppm です
発がん性
これらの物質が空気中の水分と反応してできるホスフィンが殺虫成分です。この物質は極めて毒性が強く、吸入すると肺水腫や昏睡状態になることが知られており、そもそも発がん性を評価する対象になっていません。
クロルピリホスメチル:殺虫剤/発がん性なし
有機リン系の殺虫剤で、ヨトウムシ、アブラムシ類等の害虫に効果があります。ポストハーベストの殺虫剤として以下の穀物などへの使用が認められています。ヒトの 一日摂取許容量(ADI)は0.01 mg / kg-体重です 13)。
使用される農産物と残留基準値
- 小麦:10 ppm
- 米: 0.1 ppm
発がん性
発がん性および催奇形性はありません 13)。
フェニトロチオン(スミチオン):殺虫剤/発がん性なし
有機リン系の殺虫剤であり、ポストハーベストで以下の穀物への使用が認められています。ヒトの一日摂取許容量(ADI)は 0.0049 mg / kg -体重です 6)。EUでは使用が禁止されました。
使用される農産物と残留基準値
- 小麦:10 ppm
- 米:0.2 ppm
オーストラリアにおけるフェニトロチオンの小麦への残留基準値は日本と同じ 10 ppm です。
発がん性
発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性、遅発性神経毒性および生体において問題となる遺伝毒性は認められていません 6)。
ピリミホスメチル:殺虫剤/発がん性なし
ポストハーベストで以下の穀物等への使用が認められています。一日摂取許容量(ADI)は0.004 mg / kg -体重です 7)。
使用される農産物と残留基準値
- 小麦:1 ppm
- 米:0.2 ppm
発がん性
遺伝毒性はなく、マウスでの発がん性、繁殖への悪影響は観察されていません。高用量では胎児毒性が見られたものの、これは例外と見なされるべきだとされています 7)。
ジクロルボス(DDVP):殺虫剤/発がん性なし
有機リン系殺虫剤で、かつては日本でも農薬として使われていましたが、2012 年に農薬としての登録は失効しています。防疫のための燻蒸に使われるほか、家庭用の殺虫剤の成分としても使われています。ポストハーベストで以下の穀物等への使用が認められています。また一日摂取許容量(ADI)は 0.0033 mg / kg -体重です 8)。
使用される農産物と残留基準値
- 小麦:0.2 ppm
- 米:0.2 ppm
発がん性
繁殖毒性及び催奇形性は認められていません。発がん性及び遺伝毒性を示す試験結果が得られているが、in vivo における遺伝毒性はある用量以下では認められないとされています 8)。
まとめ
- ポストハーベスト農薬は農産物を収穫した後に使うもので、輸入フルーツに使われる防カビ剤と、輸入穀物に使われる防虫剤があります。農薬という名前ですが、食品添加物の扱いで、残留基準値が決められており、基準値を上回ったものは店頭に並びません。
- ポストハーベスト農薬は、農産物の品質の低下を防ぐ、農産物の腐敗等による廃棄を減らし、農産物を安価に供給する、輸送・保管中の発生したカビなどによる食中毒を防止する、目的で使われます。
- 防カビ剤としてよく使われるものには、オルトフェニルフェノール(OPP)、チアベンダゾール(TBZ)、イマザリルなどがあり、使用している場合には、ばら売りであっても表示しなければならない決まりになっています。
- 防虫剤としてよく使われるものには、マラチオン、ピペロニルブトキシド、ピレトリンなどがあります。
- ポストハーベスト農薬は、収穫した農産物の保管中の倉庫の中や、輸送中の貨物船の中で使用されるため、検査を行う時点での残留量が多いというのは事実です。ただ安全性は、ふつうの農薬もポストハーベスト農薬も変わりません。
- 農薬や食品添加物には、残留基準値が決められています。これは化学物質を一生涯摂りつつけても人体に影響がない量である一日摂取許容量(ADI)の 1/100 に設定されていることが多いので、基本的には安心といえます。
- すべてのポストハーベスト農薬に発がん性があるわけではありません。
参考文献
1) 日本食品化学研究振興財団、残留農薬基準値検索システム
2) ヒトに対する発がん性の危険性の特定に関するIARCモノグラフ、国際がん研究機関
https://monographs.iarc.who.int/
3) 農薬・添加物評価書 フルジオキソニル、食品安全委員会、2009年7月(2009)
4) 農薬・添加物評価書 ピリメタニル、食品安全委員会農薬専門調査会、2012年4月(2012)
5) 農薬評価書 マラチオン、食品安全委員会、2014年5月(2014)
6) 農薬・動物用医薬品評価書 フェニトロチオン(第2版)、食品安全委員会農薬専門調査会、2017年5月(2017)
7) 食品安全総合情報システム、内閣府食品安全委員会
http://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu01070120149
8) ジクロルボスについて、内閣府食品安全委員会
https://www.fsc.go.jp/emerg/6.pdf
9) 厚生労働省ウェブサイト、残留農薬
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/zanryu/faq.html
10) 農林水産省植物防疫所ウェブサイト
https://www.maff.go.jp/pps/j/business/import/faq/index.html#Q109
11) 農薬・添加物・動物用医薬品評価書 チアベンダゾール、食品安全委員会農薬専門調査会、食品安全委員会動物用医薬品専門調査会、2014年8月(2014)
12) 化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP)、製品評価技術基盤機構
https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop
13) クロルピリホスメチル、農林水産消費安全技術センター
http://www.famic.go.jp/ffis/feed/info/profile/chlorpyrifos_methyl.pdf